「(仮称)こども本の森 中之島」設立記念連続講演会

文学をはじめとした良質で多様な芸術文化に直接触れることができる、子どもたちのための新たな施設「こども本の森 中之島」が、安藤忠雄氏の建築によって計画されています。設立を記念し、連続講演会を開催いたします。 第1回目は
目次
公益財団法人 文字・活字文化推進機構
© Characters Culture Promotion Organization.
2 / 3

文学をはじめとした良質で多様な芸術文化に直接触れることができる、子どもたちのための新たな施設「こども本の森 中之島」が、安藤忠雄氏の建築によって計画されています。設立を記念し、連続講演会を開催いたします。 第1回目は
大阪樟蔭女子大学児童教育学部では、「認定絵本士」を取得できる講座が開設されました。これを記念して、講演会&シンポジウムを開催しました。 ※開催の様子はこちらをご覧ください。 (大阪樟蔭女子大学ホームページ内特設サイト

朗読を通して地域の人びとをつなぎ、子どもの言葉を育てる活動の核となる朗読指導者を育てるための「朗読指導者養成講座」、2018年度(第四期)を開講しました。 詳細については、「朗読指導者養成講座」のページをご覧ください。

本キャンペーンでは、読書に距離をおく高校生を中心に、本に向き合うきっかけをつくり読書の魅力を分かち合う力を育ててもらいたいという願いを込めて冊子を作成、全国の高等学校・公共図書館に配布しました。 キャン
高校生がお薦めの本を発表し合い、参加者らが一番読みたいと思う本(チャンプ本)を決める大会、高校生書評合戦の東京都大会と首都大会を、東京都教育委員会と共催で開催しました。 【平成 29年度高校生書評合戦(ビブリオバトル
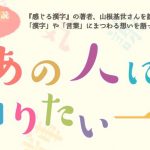
『感じる漢字』の著者、山根基世さんを講師に迎え、「漢字」や「言葉」にまつわる想いを語っていただきました。 漢字ミュージアムでは、講演聴講者対象に記念ワークショップも開催しました。
新たなテクノロジーの誕生で、人々の生活が急速に変化しています。ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)をはじめとする情報技術の発達は、人々が育む文化にも大きく影響しています。グーテンベルクによる印刷技術の発明以

国立青少年教育振興機構と文字・活字文化推進機構は、7月27日(木) から 7月30日(日) の 3泊4日、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで「読書と体験の子どもキャンプ」を開催しました。10周年目と
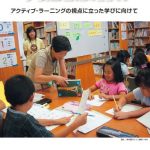
新学校図書館整備等5か年計画スタートに伴い全国学校図書館協議会、日本新聞協会、学校図書館整備推進会議とともにパンフレットを作成しました。

朗読を通して地域の人びとをつなぎ、子どもの言葉を育てる活動の核となる朗読指導者を育てるための「朗読指導者養成講座」、2017年度(第三期)を開講しました。詳細については、「朗読指導者養成講座」のページをご覧ください。
高校生がお薦めの本を発表し合い、参加者らが一番読みたいと思う本(チャンプ本)を決める大会、高校生書評合戦の東京都大会と首都大会を、東京都教育委員会と共催で開催しました。 【平成 28年度高校生書評合戦】(東京都大会予選
歴史を記し、伝え、残すのには言葉の存在が欠かせません。 人の営みは言葉によって歴史として刻まれ、それを語り継ぎ、読み継ぐことを人々は続けてきました。 将来が見通しにくい現代こそ、歴史を振り返り、歴史に学びながら新た

国立青少年教育振興機構と文字・活字文化推進機構は、7月28日(木) から 7月31日(日) の 3泊4日、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで「読書と体験の子どもキャンプ」を開催しました。9回目となる

朗読を通して地域の人びとをつなぎ、子どもの言葉を育てる活動の核となる朗読指導者を育てるための「朗読指導者養成講座」、2016年度(第二期)を開講しました。今年は規模をさらに拡大し、2クラス計60名の受講者を募りました。
高校生がお薦めの本を発表し合い、参加者らが一番読みたいと思う本(チャンプ本)を決める大会、高校生書評合戦の東京都大会を、東京都教育委員会と共催で開催しました。 【平成 27年度高校生書評合戦】(東京都大会予選) 当日
言葉で人生やビジネスが豊かになる、そんな経験はありませんか。 言葉は自分を写す鏡であり、人に何かを伝える手段にもなります。 多様なメディアに膨大な情報があふれる今こそ、言葉の力をじっくりと考えてみたいと思います。 活字

今年も、国立青少年教育振興機構と文字・活字文化推進機構主催の「読書と体験の子どもキャンプ」を開催しました。

朗読を通して地域の人びとをつなぎ、子どもの言葉を育てる活動の核となる朗読指導者を育てるための「朗読指導者養成講座」を開講しました。 詳細については、「朗読指導者養成講座」のページをご覧ください。
高校生がお薦めの本を発表し合い、参加者らが一番読みたいと思う本(チャンプ本)を決める大会、高校生書評合戦の東京都大会と首都大会を、東京都教育委員会と共催で開催しました。 【平成 26 年度高校生書評合戦東京都大会】 当
言葉の役割って何でしょうか。 それは自分を映す鏡であり、人の心を開く鍵でもあります。ネット社会に多くの文字があふれている今は、言葉が持つ役割を改めて考える良い機会です。本や新聞から得た知識、情報を通じて、人と出会い、新

国立青少年教育振興機構と文字・活字文化推進機構は、7月24日から4日間、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで「読書と体験の子どもキャンプ」を開催しました。7回目となる今年度は、全国38都府県51校の
2013年11月、千代田区・ベルサール秋葉原で、首都圏1都3県の予選を勝ち抜いた高校生は 23日に、全国の予選から勝ち上がった大学生は翌24日にそれぞれ準決勝・決勝を行い、両日ともに白熱した書評合戦が繰り広げられました
若年層の活字離れが指摘される中、読書や言葉の魅力を体験談から、科学的裏づけからなど多角的に語っていただきました。 ※ 当シンポジウムの採録記事は10月6日に日本経済新聞朝刊26、27面に掲載されました。

国立青少年教育振興機構と文字・活字文化推進機構は、7月26日から28日までの3日間、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで、平成25年度「読書と体験の子どもキャンプ」を開催しました。 子どもたちは、初
オリンピックなどを通じて、映像はもちろんのこと、文字・活字もまたスポーツの素晴らしさやアスリートたちの内面の世界を伝えてきました。アスリートたちの想像力や自己表現を支えるのは「言葉の力」です。シンポジウム「スポーツを読

国立青少年教育振興機構と文字・活字文化推進機構は、8月3日から5日までの3日間、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで、平成24年度「わくわく子ども読書キャンプ」を開催しました。 この読書キャンプは
国際競争を勝ち抜くには、どのような力が必要なのか?グローバルな人材戦略はどうあるべきか?読解力、交渉力や対話力など、日本の今日的な課題について討論していただきました。

国立青少年教育振興機構と文字・活字文化推進機構は、7月30日から8月1日までの3日間、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターで、平成23年度「わくわく子ども読書キャンプ」を開催しました。 この読書キャン